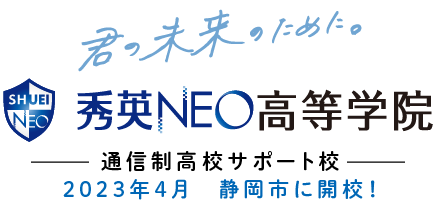- Meet Shuei! TOP
- その他
- 「話を聞いてもらえる先生」になるために──秀英教師インタビュー#01
2025.07.23
その他
「話を聞いてもらえる先生」になるために──秀英教師インタビュー#01
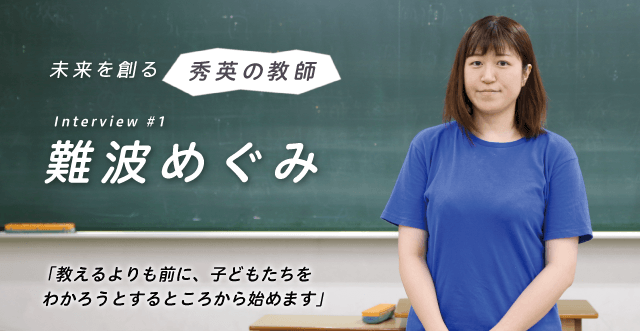
子どもって、正論を話しても、「この先生の話は聞かない」と一度思ったら、本当にまったく耳を傾けてくれなくなります。だから私はまず、“この人の話なら聞いてもいいかな”と思ってもらうことを一番大事にしています。
ただ、生徒がこちらの話を聞こうと思ってくれるまでには、かなり時間がかかり、すぐに関係が築ける子ばかりではありません。あまり自分のことについて話さない子だと、1年近くかかることもあります。そういった子がようやく自分から話しかけてくれるようになる瞬間って、本当に大切で。
そこに至るまで、好きなことは何か、今週は学校でどんな授業があったか、家族とはどういう関係か、兄弟と仲がいいのかなど、いろんな角度からお子様に歩み寄ります。
あとは最近観た動画や、好きなYouTuberの話まで拾います。たとえば生徒が「〇〇ってアニメ知ってる?」と言えば、私もあとで調べて、次の授業で「観てみたよ」と返す。それだけでも、「この先生、自分の話を聞いてくれる人だ」と心を開いてくれるんです。
そういうことを少しずつ聞きながら、「この人は自分を知ろうとしてくれている」と思ってもらえるよう、粘り強く関係を築いていきます。勉強を教える前に、人として信頼される。ここを飛ばして成績を伸ばすのは、正直無理だと思っています。
授業外の会話を通して「この先生なら話してもいい」と思ってもらえる関係づくりが、学習意欲にもつながっていくと思います。
教師として一番苦労したことはなんですか?
実は私、人前で話すのが本当に苦手で…。研修中に頭が真っ白になってしまって、声が出なくなってしまうこともありました。
それを克服するために、カラオケに一人でいって声出し練習をしたり、黒板のレイアウトを家で何度も下書きしたり、最大限の準備を重ねました。「やれることは全部やろう」と思っていたんです。
入社1~2年目は定期的に授業研修があって、社内テストも山ほどあります。落ちることもありますし、学生の頃のテストみたいにものすごく緊張します。
でもそんな成長の場があったからこそ、“教師も挑戦してるんだ”という感覚を持ち続けられました。いま生徒の前に立って話せるのは、何度もつまずいて、何度も立ち上がった経験があるからです。

「挫折」を感じたことはありますか?
正直、教室長になってからは毎日大変でした。自分が教えるだけではなく、他の教師への指導、保護者様対応、教室全体の成績管理…。気づけば、あれもこれも手が回らない。
それに、一生懸命やっているのに、生徒の成績を思うように伸ばしてあげられないこともありました。時間も足りないし、自分の力不足も痛感して。
でも、そこで学んだのが、“自分ひとりで抱え込まないこと”。教室の先生たちにお願いしたら、「いいよ、手伝うよ」と即答してくれて。
その時に、秀英予備校の塾全体で子どもを支える、というチームの力を心から感じました。頼ることは悪いことじゃない。むしろ、子どもにとってベストなサポートをするには、頼れる環境こそ必要だと学びました。
忘れられないエピソードはありますか?
中学2年生の女子生徒で、社会の授業がまったく理解できていなかった子がいました。「鎌倉幕府ってなに?」と聞かれたとき、正直、どこから教えたらいいのか分からなくなりました(笑)。でも話をよく聞くと、学校の先生と合わなくて、授業への苦手意識が強くなっていたようだったんです。
そこで、まずは話を聞いてもらえるような関係づくりから始めて、小さなハードルを毎回一緒にクリアしていきました。「これ、できるようになったね」「言われた通りやってみたら分かったでしょ」と、そんなやり取りを繰り返すうちに、彼女は少しずつ「やればできる」という感覚を覚えていきました。
最終的には、私立高校の特進クラスに合格し、本人もすごく嬉しそうに報告してくれたんです。どんな子でも、きっかけと自信さえあれば、きっと変われる。そのことを改めて教えてもらった大切な経験です。

今後、教育者として取り組んでいきたい目標はありますか?
中学生の子どもたちと接していると、「もっと早くから勉強しておけばよかった」と口にする場面に何度も出会います。そのたびに、「この子たちが後悔する前に、始めるきっかけがあればよかったのに」と感じます。
だから今、私が目指しているのは、小学3年生や4年生という早い段階で、子どもたちが「勉強って意味があるかもしれない」「やってみようかな」と前向きに思える環境をつくることです。
“学び”が苦手になる前に、知る喜びや、できるようになる感覚を育てていきたい。それは単に学力の底上げではなく、自信や好奇心の土台になるからです。子どもたちが「勉強はイヤなもの」になる前に、ポジティブな入口を増やす。それが、今の自分にできる一番の挑戦だと思っています。
保護者の皆さまへ伝えたいメッセージを教えてください。
学校の先生と塾の教師は、少し立場が違います。学校の先生の多くは教育学部を出てすぐに教壇に立ちますが、私たち塾教師には、たとえば私のように一度他業種を経験してきた者も多くいます。
だからこそ、学校の先生方とは違った視点で子どもたちを見て、話を聞ける立場だと思っています。生徒一人ひとりの背景を知ろうとし、深く関わろうとする姿勢が、塾での信頼関係づくりには欠かせないと感じています。
私自身もそういった観点から、子どもたちの成績を上げることだけでなく、その子の“人としての成長”にも責任を持ちたいと思っています。
子どもたちは、自分がどれだけ支えられているかに気づきにくい。私自身も、学生時代はあまり親に対して感謝することができていなかったなと感じますが、大人になり社会に出て初めて、「私は恵まれてたんだ」と気づく瞬間が何度もありました。
ごはんが出てくるのも、塾に通わせてもらえるのも、当たり前だと思わずに感謝すること。
「今ある環境は、誰かがあなたのために用意してくれているものなんだよ」と少しずつ授業の中でも伝えるようにしています。自分の立場や環境に気づき、感謝できる子に育ってほしい、という想いからです。
ご家庭の中でお子さまを支えているすべての保護者の皆さまに、心から感謝しています。私たちはそのバトンを、教室でしっかりと受け取り、お子さまの力になる存在でありたいと思っています。
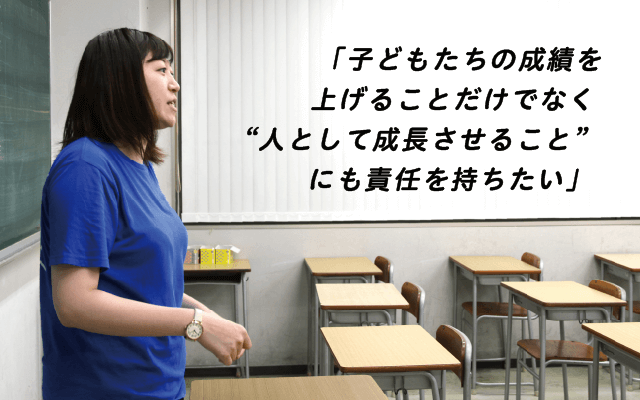
難波めぐみ プロフィール (2025年7月時点)
●所属校舎/静岡本部校
●入社年/2016年
●担当学年/小学1年~6年
●担当教科/国語・英語・社会
●出身地/静岡県三島市
●座右の銘/ワンランク上を目指す